Special 【2026年1月施行】法改正前に受けたいセミナー・講演特集|下請法改正のポイントを徹底解説

取引適正化に向けた準備はお済みですか?
2026年1月、「下請代金支払遅延等防止法」と「受託中小企業振興法」が改正・施行されます。
近年、労務費・原材料費・エネルギーコストの急激な上昇を受け、政府は「物価上昇を上回る賃上げ」の実現を掲げています。
そのためには、事業者が賃上げの原資を確保できる仕組みが不可欠です。
中小企業をはじめとする事業者が原資を確保するには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる、いわゆる「構造的な価格転嫁」の実現が重要とされています。
しかし実際には、協議に応じない一方的な価格決定や、受注側に負担を押し付ける商慣習が残っており、価格転嫁の妨げになっていました。
こうした課題を解消し、取引の適正化を進めるために今回の「下請代金支払遅延等防止法」改正が行われ、2026年1月1日(令和8年1月1日)から施行されます。
今回の改正は、価格転嫁の促進、支払方法の適正化、物流委託の追加など、発注側・受注側双方に大きな影響を及ぼす内容です。
経営者や人事担当者にとっては、契約条件の見直しや社員への周知を今から進めておくことが不可欠です。本特集では、法改正のポイントと、それをわかりやすく簡単に解説してくれる講師をご紹介します。
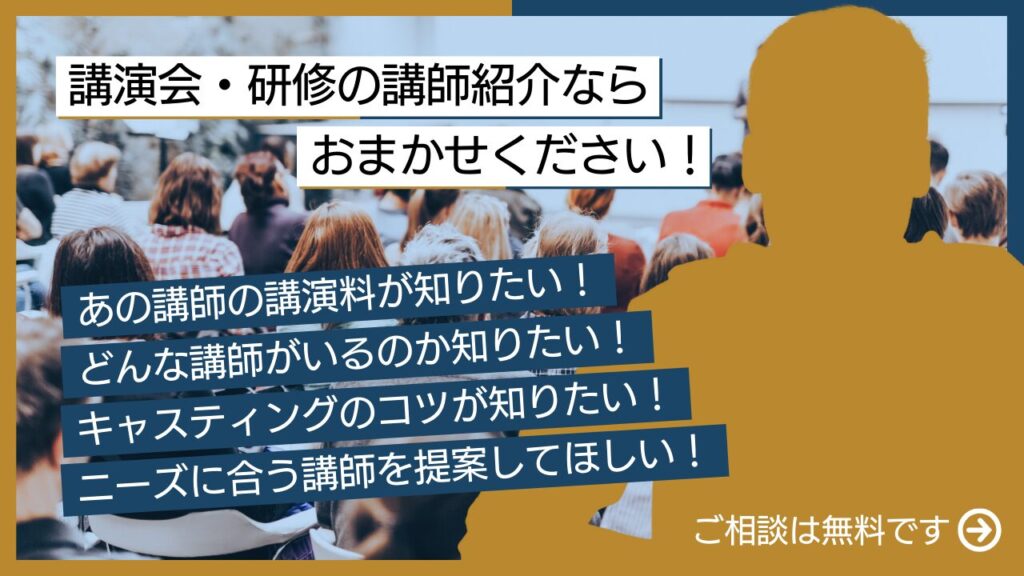
改正法のポイントをわかりやすく整理
経営層・人事担当者が知っておくべき改正内容
・価格協議を適切に行わない代金決定の禁止
→ 一方的な価格据え置きはNGに。交渉の記録も重要になります。
・手形払いの禁止
→ 現金払い・振込が基本に。資金繰りや支払条件の見直しが必要です。
・運送委託の追加
→ 製造・販売だけでなく、物流も規制対象に。契約範囲の確認を。
・従業員基準の拡大
→ 保護対象となる企業が広がり、自社も新たに対象になる可能性があります。
・行政による指導・助言の強化
→ 違反のリスクが増大。事前の準備が不可欠です。
2026年の下請法改正は、経営者や人事担当者にとって、自社の取引や契約の見直しを行う絶好のタイミングです。特に価格協議や支払方法、契約範囲の確認など、事前に準備しておくことで、トラブル防止だけでなく、社員や取引先との信頼関係強化にもつながります。今回ご紹介したポイントを押さえた上で、実務に役立つセミナーや専門家の講演を活用することをおすすめします。
改正法のポイント①協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
改正の背景
労務費・原材料費・エネルギーコストなどが上昇する中、価格協議を行わずに据え置いたり、一方的に不利な価格を決定する取引慣行が問題視されてきました。これでは中小事業者が適切に価格転嫁を行えず、賃上げの原資確保が難しくなります。
改正の内容
今回の改正では、買いたたきとは別に「対等な価格交渉を確保する」観点から、以下のような行為が禁止されます。
・中小受託事業者からの価格協議の求めに応じない
・委託事業者が必要な説明や情報提供をしない
・一方的に代金を決定し、中小受託事業者の利益を不当に害する
企業にとってのポイント
・今後は「協議のプロセス」自体が問われる
・契約・取引条件の見直し、説明責任の明確化が必要
・担当部門への教育や社内ルールづくりが早急に求められる
改正法のポイント②手形払等の禁止
改正の背景
従来、支払手段として手形が多く用いられてきましたが、これは実質的に受注者に資金繰りの負担を強いる商慣習となっていました。結果として、中小事業者の経営を圧迫する要因になっていたのです。
改正の内容
今回の改正では、中小受託事業者を守るために、以下のような措置が取られます。
・本法上の支払手段として「手形払」を全面的に禁止
・電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する金額(手数料等を含む満額)を得られない場合は使用不可
企業にとってのポイント
・手形を使った取引は今後不可 → 代替手段(現金・振込など)の準備が必要
・「支払条件の見直し」が急務
・グループ会社や取引先を含めた資金繰りの影響をシミュレーションしておく必要がある
改正法のポイント③運送委託の対象取引への追加
改正の背景
これまで発荷主から元請運送事業者への委託は下請法の対象外で、独占禁止法の物流特殊指定で対応してきました。
しかし現場では、立場の弱い物流事業者が「荷待ち・荷役を無償で強いられる」などの不公平な取引慣行が深刻化しており、改善が強く求められていました。
改正の内容
・発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を、新たに下請法の対象に追加
・これにより、物流分野での不公正な取引に機動的に対応可能に
企業にとってのポイント
・発荷主(荷主企業)は、従来以上に「荷待ち・荷役をどう扱うか」を明確化する必要あり
・無償対応を前提とした契約・運用はリスクに
・物流部門・購買部門と連携し、委託条件の見直しを早めに進めることが重要
改正法のポイント④従業員基準の追加
改正の背景
事業規模は大きいにもかかわらず、資本金が少額であることで下請法の適用対象外となるケースが存在。また、発注者が受注者に対して「適用逃れ」を目的に増資を求める事例も確認されており、公平性が損なわれていた。
改正の内容
・適用基準に「従業員数」を新たに追加
・資本金要件に加え、以下の基準を満たす場合も対象に含める
◆ 製造委託などの場合:従業員数 300人以下
◆ 役務提供委託などの場合:従業員数 100人以下
企業にとってのポイント
・発注側は「資本金だけで対象外」とは言えなくなるため、取引先の従業員数も確認が必要に
・受注側(中小受託事業者)にとっては、従業員規模に応じた保護が受けられる範囲が広がる
・契約書・取引条件の見直し時に、新しい基準を意識しておくことが必須
改正法のポイント⑤面的執行の強化
改正の背景
現在、事業所管省庁には「調査権限」のみが与えられており、公正取引委員会や中小企業庁との連携による十分な執行が課題となっていた。また、中小受託事業者が「トラック・物流Gメン」など事業所管省庁に通報した場合、現行制度では「報復措置の禁止」の保護対象外となっていたため、申告しにくい状況があった。
改正の内容
・事業所管省庁の主務大臣に「指導・助言権限」を新たに付与
・さらに「報復措置の禁止」の申告先を拡充し、公正取引委員会・中小企業庁長官に加えて、事業所管省庁の主務大臣も対象とすることで、中小受託事業者の申告環境を改善
企業にとってのポイント
・発注側は、複数の行政機関からの指導・助言を受ける可能性が高まるため、より厳格なコンプライアンス体制が必要に
・受注側は、相談窓口が増えることで安心して声を上げやすくなる
・特に物流や製造など業界特化の所管官庁による直接的な関与が想定されるため、業界ごとのルールやガイドラインも併せて確認しておくことが重要
改正法のポイント⑥「下請」等の用語の見直し
改正の背景
・従来使われてきた「下請」という言葉は、発注者と受注者が「上下関係」にあるような印象を与えるとの指摘があった
・時代の変化に伴い、大企業側でも「下請」という表現は使われなくなってきており、より対等なパートナーシップを重視する言葉への転換が求められていた
改正の内容
・用語を以下のように改正
◆ 「親事業者」 → 「委託事業者」
◆ 「下請事業者」 → 「中小受託事業者」
◆ 「下請代金」 → 「製造委託等代金」
・法律の題名も変更
◆ 「下請代金支払遅延等防止法」
→ 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
企業にとってのポイント
・契約書や社内文書での用語の見直しが必要
・社内外のコミュニケーションにおいて「下請」という言葉を使わず、対等な関係を前提とした表現に切り替えることが推奨される
・ブランドイメージやパートナーシップ強化の観点からも、発注者・受注者の関係性を「上下」ではなく「協働」として表す流れが加速する可能性
改正法のポイント⑦その他の改正事項
改正の背景
・製造委託の対象物が「金型」に限られており、木型・治具など同様に製品作成に不可欠なツールが対象外となっていた
・書面交付義務や遅延利息の規定についても、制度運用上の不備や不明確さが指摘されていた
・勧告制度においても、違反が是正済みの場合に対応が不明確であり、実効性に課題があった
改正の内容
・対象物の拡大:木型・治具なども製造委託の対象物に追加
・書面交付義務の見直し:受託事業者の承諾有無にかかわらず、必要記載事項を電磁的方法で提供可能に
・遅延利息の拡充:代金減額についても遅延利息を適用し、60日経過後から支払いまでの期間に利息支払いを義務化
・勧告規定の整備:違反行為が是正済みでも、再発防止策などの勧告が可能に
企業にとってのポイント
・製造委託を行う企業は、金型以外のツール(木型・治具等)も契約対象に含める必要あり
・書面交付はペーパーレス化が進む一方で、内容の正確性・証跡管理がより重要に
・減額行為も遅延利息の対象となるため、安易な減額は大きなリスクに
・違反が「すでに是正済み」でも勧告を受け得るため、コンプライアンス体制の事前整備が必須
今回ご紹介した2026年の下請法改正ポイントは、経営層や人事担当者が事前に押さえておくべき重要事項ばかりです。価格交渉や支払方法、契約範囲の見直しなど、自社の実務に直結する内容も多いため、早めの対応が安心です。必要に応じて、法改正対応のセミナーや専門家講師の活用も検討してみてください。
2026年下請法改正に対応!おすすめセミナー・講演例
実務対応を学び、自社の備えを強化
購買担当者、営業担当者、経営層向け「価格交渉力強化セミナー」
経営者、コンプライアンス・法務部門、管理職向け「法改正対応コンプライアンス研修」
物流部門、購買部門、経営層向け「物流・運送取引の適正化セミナー」
経営者、部門長、人事担当者向け「公正な取引文化づくり講演」
各企業の状況に応じて、講演内容をカスタマイズすることも可能です。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
価格交渉力強化セミナー
背景
2026年の下請法改正により、「協議に応じない一方的な価格決定」が禁止されます。発注者・受注者双方が、適切な価格協議・価格転嫁の実践スキルを身につけることが経営リスク回避の観点から必須となっています。特に、原材料費や労務費の上昇に伴う価格交渉力は、取引関係の公平性を保つための重要な要素です。
セミナー内容
・原価上昇に伴う価格調整の具体的な説明方法
・客観的データ・コスト計算を活用した説得力ある交渉手法
・対等な立場でのロールプレイによる交渉スキルの実践演習
・契約書や取引条件に反映するための実務アドバイス
対象
購買担当者、営業担当者、経営層
-

大久保雅士
メンタリスト ビジネス心理コンサルタント
メンタリスト⽇本チャンピオンが教える!!! ビジネ…
-

金森努
有限会社金森マーケティング事務所 取締役/青山学院…
わかる!使える!業務に活かせる! 顧客視点で考え…
-

一圓克彦
リピーター創出専門コンサルタント/一圓克彦事務所 …
0円で8割をリピーターにする集客術! ~あらゆる…
法改正対応コンプライアンス研修
背景
支払手段の見直し(手形禁止、減額規制)、対象拡大(従業員基準・運送委託)、報復措置防止の強化など、改正下請法の規定は多岐にわたります。法改正を正しく理解し、社内で統一した対応策を実行するための部門横断的な研修が必要です。
セミナー内容
・2026年改正下請法の全体像と施行スケジュール
・違反リスクや実際の制裁事例に基づくケーススタディ
・各部門が取るべき具体的アクションチェックリストの作成
・社内コンプライアンス教育や契約書レビューの実務ポイント
対象
経営者、コンプライアンス・法務部門、管理職
-

田中直才
社会保険労務士/企業危機管理士/外国人採用コンサル…
実践カスタマーハラスメント対策
-

小菅昌秀
サミット人材開発株式会社 代表取締役/一般社団法人…
クレーム・カスハラ対応研修
-
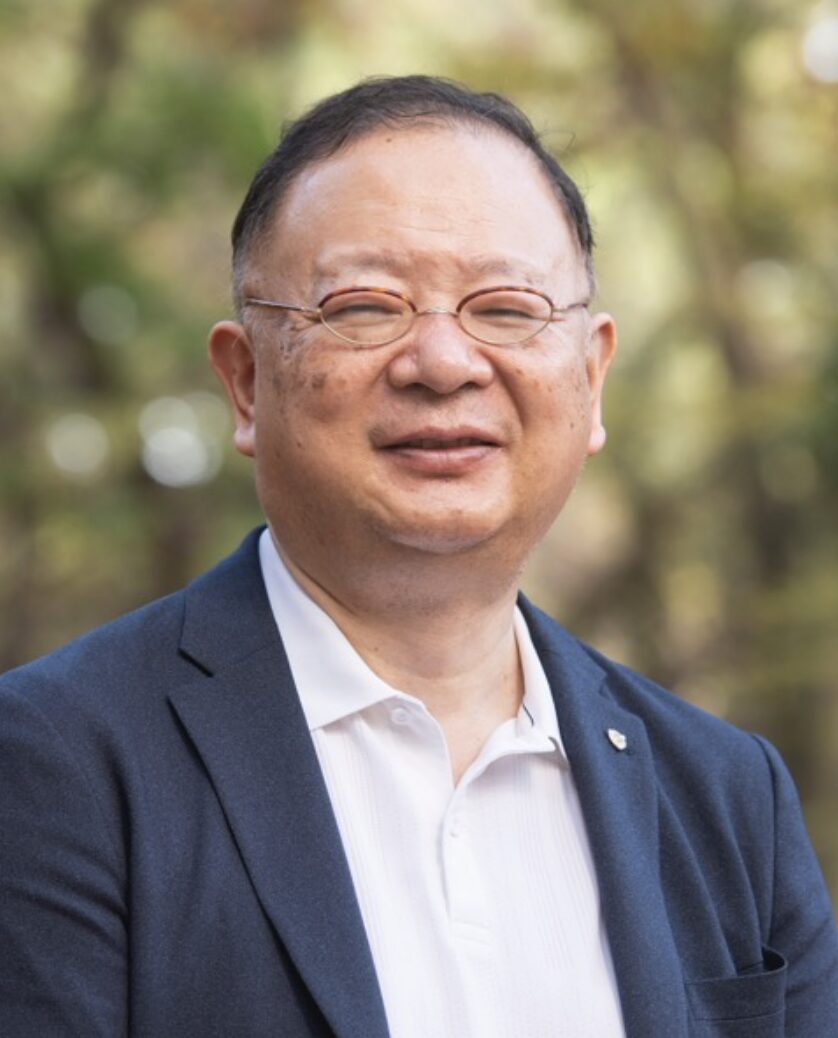
高島徹
株式会社決断力 代表取締役
人材の採用と定着 効果的な採用と人材育成で業績ア…
物流・運送取引の適正化セミナー
背景
新たに「運送委託」が下請法の対象となり、荷役や荷待ちの無償対応など不公正慣行が問題視されています。物流・運送部門に直結するテーマであり、サプライチェーン全体の取引適正化を目指す企業に必須です。
セミナー内容
・荷主企業が注意すべき2026年改正ルールの解説
・物流現場で発生しやすい不公正慣行と改善事例
・サプライチェーン全体での価格転嫁と適正取引の実践方法
・契約書・運用ルールの改定ポイント
対象
物流部門、購買部門、経営層
物流や運送の現場は法改正の影響を直接受けやすい分野です。自社の契約や運用ルールを見直すために、まずは専門講師への相談やセミナー受講をご検討ください。
公正な取引文化づくり講演
背景
「下請」から「中小受託事業者」への用語変更は、取引関係を上下関係から協働関係へシフトする象徴的な改正です。企業ブランドの信頼性向上や社員教育にも役立つ講演です。
セミナー内容
・取引関係を「協働」として捉える新しい発想
・公正取引を通じた企業ブランド強化の事例
・社内外での対等なパートナーシップの実現方法
・改正法に基づく組織文化・人材育成の考え方
対象
経営者、部門長、人事担当者
『下請』から『中小受託事業者』への言葉の変化は、企業文化の在り方を見直す良い機会です。取引の公平性と社員教育の両面から学べる講演は、経営層に特におすすめです。
実践!ケースで学ぶ下請法改正対応ワークショップ
背景
条文だけでは理解しにくい改正下請法。実際の取引ケースを通じて、どの行為が違反になるか、ならないかを実務レベルで学べるワークショップです。
セミナー内容
・減額・支払遅延・受領拒否などの典型的な違反事例の紹介
・グループディスカッション形式での判断演習
・自社取引事例を持ち込み、専門講師とともに改善策を検討
・実務に即した契約書や社内手順の見直しポイント
対象
管理職、実務担当者、購買・物流・法務部門
条文だけでは理解しにくい改正下請法も、実際の取引ケースを通じて学べば社内での対応がスムーズになります。自社事例を持ち込み、講師と一緒に実践的に考える機会としてご活用ください。
講師へのお問い合わせはこちら
「法改正前にセミナーを開催したい」「自社に合う講師を紹介してほしい」という方は、下記フォームよりご相談ください。経験豊富な講師が、経営者・管理職・担当者向けに法改正のポイントを分かりやすく解説します。
Hitonovaの講師陣は現場経験やコンサル経験が豊富。企業の実務に即したカスタマイズ対応も可能です。
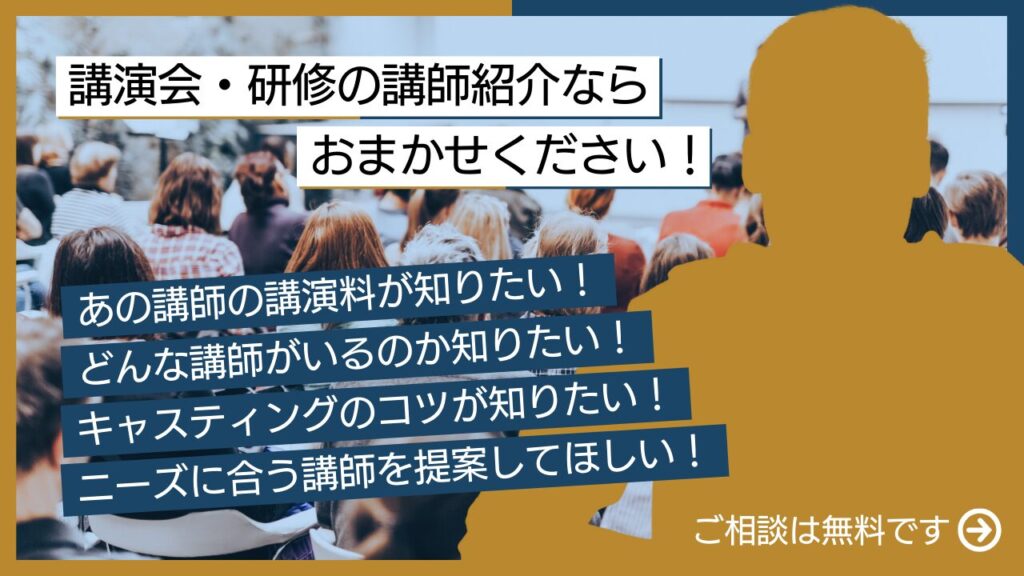
施行後に慌てないために、今のうちに準備を整えておきましょう。
Contact お問い合わせ
ご相談は無料です。
ホームページに掲載のない講師も対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
候補に入れた講師
-
候補がありません。
